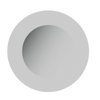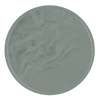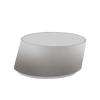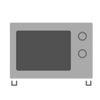Journal

サステナブルコレクションvol.2「海水」 新しい時代の器が、新しい時代をつくる。
7月20日、ARASの新商品としてサステナブルコレクションvol.2「海水」が発売された。 ローンチを記念し、ARAS開発者の石川工業株式会社専務取締役の石川勤さんと、プロダクトデザインを手掛けるクリエイティブチームsecca代表の上町達也さん、NAGORI®を開発した三井化学株式会社の近藤淳さんの鼎談が行われた。 本編に入る前に、鼎談の中で上町さんが言ったことばを紹介する。
もっと見る
いつもARASをご愛顧くださりありがとうございます。 ARAS製品の電子レンジ使用について、お客様から多くご要望をいただき、電子レンジ使用に伴う器の形状・質感の変化や、人体への影響などについて、改めて様々な角度から検証いたしました。
もっと見る
3月20日、ARASの新商品「キッズシリーズ」が発売された。ARASのInstagramでは発売を記念するライブ配信が行われた。 「食べる楽しさ」を親子でシェアできるというコンセプトを元に開発された今シリーズは、食を通して子どもの好奇心や喜びを引き出し、料理の幅を広げ、親子が共に過ごす食卓の風景を豊かにするアイテムだ。器・カトラリー共に、素材、色、カタチは通常の大人用と同じデザインが施されている。そこには、デザイナーたちの想いが込められていた。 今回の配信では、ARASのプロダクトデザインを手掛けるクリエイティブチームsecca代表の上町達也さんとseccaのクリエイティブリーダーである柳井友一さんがキッズシリーズの魅力を語った。また、ARASのマーケター山中沙紀さんには子を持つ親の立場から普段使いのARASについて話を伺った。 文 / ファシリテーター:嶋津(ダイアログ・デザイナー) 大人と同じ食体験を 嶋津:キッズシリーズをおつくりになったきっかけを聴かせてください。 上町:兼ねてよりユーザーの皆様から「キッズ用の器がほしい」とのご要望がありました。また、チームメンバーのほとんどが子を持つ親であり、いただいた声が僕たちにとって“自分ごと”であったことが大きな理由です。重要なことは「ARASらしいキッズシリーズとは?」を考えることです。 世の中を見渡してみると、子ども向けの商品はポップで丸くてかわいいアイテムばかりだと気付きました。安全性を考慮した上で設計され、“子どもらしさ”を表現した商品であり、それが一つの選択肢だとは思います。 ただ、自分の子どもの頃の記憶に立ち返った時、必ずしも「子ども=かわいいモノ」でなくとも良いのではないか。そのような想いがありました。 * 「いち早く“ホンモノ”に触れたかった」 クリエイティビティの種は、上町さんの原風景にあった。お父さまの職業柄、家にはたくさんのメカが並んでいた。その一つひとつにこころをときめかせた。中でも憧れていたのは、お父さまが大切に扱っていた巻き上げ式のフィルムカメラ。「あのカメラで写真を撮りたい」。少年時代の上町さんは想いを募らせた。でも、「どうせ壊すだろう」と触れさせてさえもらえなかった。代わりに買ってもらったおもちゃのカメラは、本当の意味では上町少年のこころを満たすことができなかった。 * 上町早くから“ホンモノ”に触れることで、多くのことを学べると思っています。性能はもちろんのこと、扱う際に美しい所作も自然と身につきます。だから“ホンモノ”は遠ざけるべきではなく、触れる機会を増やしていく。それも、あるべき考え方の一つであると思っています。 僕たちは“こだわりがある人の普段使い食器”を目指し、家庭の食体験をよりおいしく、より楽しくすることを思索してきました。素材にも、色にも、カタチにも「おいしい」に繋がる想いや意図があります。子どもが使用する器であっても、その価値は大きく変わらない。だからこそ、子どもに対しても大人と同じ扱いをする。そこが基軸となっています。 * ARASは「食」を豊かにするブランドであり、“食体験の時間”そのものをデザインしてきた。その中で、大人だけがARASに触れ、子どもは違う食器を使う状況に疑問を抱いていた。子どもが親と同じモノを使いながら、食卓を共に過ごす。「それがARASらしい回答だと思った」と上町さんは話した。基本的な装いは大人用と同じ思想で、安全性を確保しつつ、子どもが使用しやすいサイズにチューニングした。 * 嶋津「子ども扱いしない」という姿勢は、言い換えると「子どもを対等に見ている」とも表現できますね。“子どもらしさ”を決めつけるのではなく、キッズシリーズからは子どもに対するリスペクトを感じます。 上町スタンスとして「子どもを対等に見るべき」というよりも、「選択肢の幅を広げる」という意味合いの方が大きいように思います。世の中に既に同じ考え方の商品があれば、アプローチは変わっていたかもしれません。僕たちのリサーチの中では、大人と同等に選べるモノはほとんど見受けられませんでした。だから、それをARASが形にする。“選べる状況”を提案することにも価値があると思っています。 嶋津ARASには「食体験のアップデート」という考え方がありますよね。大人はもちろんのこと、それを子どもの頃から体感できることは、食育にも繋がりますね。 上町2、3歳になると、道具を使って食べ物を口にしはじめます。うまく道具が扱えないと、「食べる」という行為自体が嫌いになるケースもある。たとえば、スプーンで食べ物をすくうことができない、など。それは、子どもの安全性を考慮して、道具を分厚く(丸く)し過ぎたことが原因の一つだと思っています。 ARASは樹脂素材であるため、殺傷性を抑えることができます。素材の力によって安全を確保しながら使いやすさを追求し、大人と同じ装いで食事ができる。上手に食べることができることで「おいしい」と結びついたり、「食べる」という行為が好きになってゆく。さらには、親御さんとのコミュニケーションにも繋がります。 * 上手に食べることができた体験が「おいしい」という感覚や「楽しい」という感情へと結びつく。子どもの成長と共に、自尊心も養うことに繋がってゆく。ARASの魅力は、ライフスタイルに溶け込んで、それぞれのこころを豊かにすること。上町さんの考え方からも伝わるように、決して無理強いはしない。新しい価値観を提示して、“選べる状況”を提案してゆく。 デザインに息づくきめ細かな配慮 嶋津商品の特徴に関してはいかがでしょう? 柳井キッズシリーズの装いは、基本的に大人用と同じ考え方です。ただ、単純に縮小したわけではなく、所々相応しいカタチへ再設計しています。深皿スクープは、大人用もキッズ用もカレーやスープなどの料理をすくいやすいデザインですが、器の安定化のためにボリュームのある肉厚に調整しました。重心が下にあるため倒れにくく、子どもが安心して扱えます。 カトラリーは、持ち手が円筒状になっており、大人と子どもそれぞれが自分の手にフィットする部分で支えることができます。口元の厚みは、極端に薄いと口をケガさせてしまう危険性があるため、大人用のスプーンと共通して0.8㎜の厚みに。小さな子どもは口の幅が狭いので、そこに照準を合わせています。離乳食から使いはじめることが可能です。 ナイフは、ノコギリ刃の機能を踏襲していて、大人用と基本的な切れ味は変わりません。ただ、子どもでも力を伝えやすいように、刃と柄の比率を調整しています。大人用では、およそ一対一の割合ですが、キッズシリーズでは刃を若干短くしています。「切る」という動作は、人差し指でナイフを押し込みながら力を加えます。支点と力点のポイントをずらして、負担なく切ることができます。 嶋津サイズが小さいだけではなく、ARASの思想を基準とした細やかなデザインがそれぞれのプロダクトに落とし込まれている。キッズシリーズと言いながらも、大人でも十分に使えそうですね。 上町うれしい視点です。キッズシリーズは、子どもに使用していただけることを目的にしたサイズ感ですが、当然のことながら大人でも使用していただけます。たとえば、小さいスプーンであれば子どものメインスプーンとして、一方で大人にはティースプーンやデザートスプーンとして使用いただける。その点も考慮しています。 柳井また、どの器も裏側に微かな凹凸をつくり、安定を保たせています。まったく平らにすると、テーブルのわずかな傾きによってカタカタと動いてしまう。テーブルとの接地面は、縁のみであるため、全面が擦れて傷つくことがありません。また、一般的な器には「高台(こうだい)」と呼ばれる縁がありますが、洗浄の際に水滴が残りやすい部分でもある。それらの点を解消する構造とデザインをしつらえています。 左:カトラリーは素材の性質を活かして、器と接触してもカチャカチャと不快な音を立てず、木に近いやわらかな印象の響きをもたらす。右:スタッキングした深皿スクープ(大と中)。片付けられた佇まいまでデザインが落とし込まれている。 おいしい時間 嶋津ここでARASを普段使いしている山中沙紀さんに、実際に子どもを持つ親の立場からお話をお伺いします。 山中私には二歳になる息子がいるのですが、朝食ではななめ小鉢にヨーグルトやフルーツを盛り付けて、デザートスプーンを使って食べています。デザートスプーンは、ななめ小鉢との相性も良く、とても食べやすそうな印象です。 昼食や夕食では、中皿ウェーブを使用しています。ただ、カレーライスやパスタなどの場合、スタンダードな深皿スクープのサイズだと大き過ぎる印象がありました。今回キッズシリーズで中サイズが登場するので、盛り付けるにはちょうどいいサイズ感だと思っています。 柳井私にも、もうすぐ五歳になる息子と二歳の娘、二人の子どもがいます。山中さんの仰る通り、既存の深皿スクープでは、子どもの分量にしては余白が多かったので、料理の見栄えが少し寂しい状態でした。キッズシリーズによって、盛り付けもより美しくできそうです。子どものテンションが上がって食事を楽しんでいる光景が目に浮かびます。 山中スプーンに関しても、デザートスプーンと長さは同じなのですが、口元が小さくなる。二歳の子どもにとっては、より収まりやすく大口を開けなくてもしっかりと食べることができるサイズ感ですので、カレーライスなどとの相性が良いのではないでしょうか。キッズシリーズの登場で、盛り付けや料理の幅が増えることが楽しみです。 あと、「割れない」という安心感があるので、子どもに出している食器は気付けばARASの器が並んでいます。 嶋津特にお子さまがいらっしゃると「割れない、傷つかない」という点はうれしいですね。 山中最近では、盛り付けた料理を子どもたちにキッチンからテーブルまで運んでもらっています。キッズ用のサイズだったり、「割れない」安心感があると、心置きなく二歳の子どもにお皿を渡せます。配膳から食事をするところまで、親子で一緒に楽しめることはうれしいですね。 嶋津「食べる」だけでなく、料理の準備や後片付けなどでもコミュニケーションが生まれている。「今、ここ」での食体験を共有するだけでなく、それが親子の思い出になったり、コミュニケーションが集積された先に育まれる感受性の豊かさにもつながっているように思います。キッズシリーズは、“未来へのギフト”のような印象を受けました。 上町まさに仰る通りで、ARASチームで常々話していることは、「おいしい体験」は、単純に“食べる行為”だけではありません。「何を作ろうか」と料理を考えるところから既にはじまっています。食材を選んだり、お皿を選んだり、調理をしたり、家族で会話したり。子どもが安心して使用できる食器なら、落としたり割れたりする心配をしなくてもいい。料理の味や家族との会話など、「楽しむこと」に集中することができます。 “食事”という一連の流れで浮き上がってくる気がかりや小さなストレスを、素材とデザインによって解決してゆく。それが、結果的に準備から片付けまでを含めた“食体験”を豊かにできる。 家族の会話や感情を共有することが、トータルとして「おいしい時間」だと思っています。 家族で過ごす食事の時間が楽しいから、器も、料理も、家族も、会話も、すべてを大切にしたい。そう思える時間を積み重ねた先、子どもたちはどのように育ってゆくのか。三人の話を聴きながら、ARASが描く未来を体験してみたいと思った。 ARASでは、キッズシリーズ発売のイベントとして「Oyako RESTAURANT」を東京と金沢で開催をおこなった。今後も全国各地でパートナーとなるレストランやゲストと共に食体験イベントを展開してゆく。
もっと見る
【イベント開催のお知らせ】ARAS「Oyako RESTAURANT」 東京 東麻布”Restaurant L'aube”
イベントの想い この度、G.W.の5/3-5/4にRestaurant L'aube様と「Oyako RESTAURANT」を開催致します。先駆けて、3月5日(土)にARASキッズシリーズ発売のプレスイベントとして「Oyako RESTAURANT」を開催しました。
もっと見る
「あなたにとっての“サステナブル”とは?」~ARASのビジョンを語り合った空間~
2021年12月上旬、ARASのInstagramでライブ配信を行った。ARAS開発者の石川工業専務取締役の石川勤さんと、プロダクトデザインを手掛けるクリエイティブチームsecca代表の上町達也さんがARASのビジョン、そして、サステナブルの取り組みについて語った。「あなたにとってのサステナブルとは?」その問いかけに、視聴者の皆さんからもたくさんコメントが届く。リアルタイムで登壇者と交流しながら、共に“サステナブル”について考える場となった。最後には、ARASの新シリーズ「サステナブルコレクション」の発表が行われ、ライブは盛り上がりを見せた。文 / ファシリテーター:嶋津(ダイアログ・デザイナー)________________________________________ ARASが生まれたきっかけ 当初、「テーブルウェア」を軸にすることさえ決まっていなかった。樹脂を通して文化をつくり、世界をより良く変えてゆく。生活に寄り添い、価値を共有できるアイテムは何か。そこには、数えきれないほどの模索と思索があった。嶋津まず、視聴者の皆さんにARASというブランドのコンセプトを共有できればと思っています。そのためには、ブランドが生まれたストーリーからお伺いすることが最もわかりやすいと思うのですが、きっかけから誕生までのお話をお聴かせください。 上町ブランド立ち上げる2年ほど前から、デザイナーとして石川樹脂工業さんと関わらせていただいていました。当初、議論していたことは環境問題について。世間では、海洋ゴミの問題に代表されるプラスチックの存在意義が問われていた時期でした。印象に流されるのではなく、「本質的な原因は何か」を立ち止まって丁寧に考えなければいけません。“プラスチック”という素材に全ての責任を負わせることは、少し短絡的ではないか。問題はそこではなく、「モノを捨てる行為」や「海に流される仕組み」にあるのではないだろうか。環境や人にとって本当の意味で“良い未来”とは何か。僕たちは“樹脂”という素材で何ができるのか。樹脂の持つ価値や可能性を、もう一度丁寧に見直し世の中と紡ぎ直す。石川さんと議論を重ねながら、僕自身も多くのことを学んでゆきました。そして、僕たちの想いや思考を純度高く共有するためには、新しく1からブランドを立ち上げ、世の中に届けた方がより真価が伝わるのではないかという発想に至りました。 石川コンセプトづくりに1年以上かけています。ARASの立ち上げにおいて、最も時間のかかったポイントです。テーブルウェアに行き着くまでにも、多くの議論を重ねてきました。石川樹脂工業は、輪島塗や山中塗などの漆器の木地づくりにルーツがあります。また、金沢という都市は「食」の一大拠点でもある。私たちにも深い愛着があり、文化として「食」との親和性が高い。「食」と「サステナブル」を組み合わせ、私たちらしいブランドを育てていくことに決めました。 嶋津ブランドが生まれてコンセプトが決まったのではなく、明確なコンセプトが先にありブランドが立ち上がった。芯のあるコンセプトだから、次々とプロダクトに落とし込んでいけるのですね。“ARAS”という思想は、テーブルウェアだけでなく、ライフスタイルや、今回のライブ空間といったコミュニケーションにもつながっている。________________________________________視聴者からのコメントとして、数々の「わたしにとってのサステナブル」が届いた。「あるものを大切に扱い、使い捨てしないこと」、「レジ袋は控えて、エコバックを使用すること」、「伝統を継承し、文化を次世代に伝えること」。さらに、ARASユーザーの6歳の子どもは「ゴミはちゃんとゴミ箱に捨てる、おもちゃで遊んだ後は元の場所へ戻す」と答えてくれた。一人ひとりそれぞれの“サステナブル”がある。そして、この問いについて考えることが既に一つの“サステナブル”であるのかもしれない。________________________________________ モノづくりから見たサステナブル 嶋津コメントを読ませていただくだけで多様なサステナブルが存在することにあらためて気付かされます。モノづくりの観点から、二人にとってのサステナブルについても聴かせていただけますか?石川この点に関して、個人的に強い想いがあります。私には、外資系大手企業から父の会社(石川樹脂工業)に戻ってきたという背景があります。 “サステナブル”と言えば、多くの人はまず地球環境やエコについて思い浮かべるのではないでしょうか。先ほどのコメントで「次世代に伝える」とありましたが、私はその点を忘れてはいけないと思っています。皆さんは、私たちモノづくりの人間が直面している問題をご存知でしょうか。それは、後継者問題です。 事業継承が進まない。理由はシンプルで、後継ぎがいないのではなく、事業を継ぐほどの儲けがないからです。下請け会社は不当に買い叩かれ、最低賃金ぎりぎりのところでなんとか工面しています。これらの中小企業が、日本のモノづくり、ないしは私たちの生活を支えている。私が石川樹脂工業へ戻ってきた時、その現状を知り、大きなショックを受けました。この課題を解決することは、日本のモノづくりを次世代に伝えるためには不可欠です。ARASで取り組んでいるのは、ロボットやAIによる作業の自動化です。「人の手」を不用意に入れないことで省人化を進め、人が“人らしく”、人としての価値を発揮できるエリアでモノづくりに集中することを実現しました。 労働集約型のビジネスから脱却することで、最低賃金以上の給料を出せるようになります。弊社でも、給料を上げる努力や休日を増やす試みによって、現状に変化を起こそうとしています。そのような取り組みが周りの企業を触発すれば、日本のモノづくりを次世代につなげるモデルケースになるのではないか。地球環境の問題と並列して、「モノづくりを次世代へ継承すること」に、積極的に取り組んでいます。上町僕の考えるサステナブルは、「価値の持続」です。その人、その人にとってのモノを愛せる時間。愛せるモノは、大事にします。大事にすると、永く使う。そうすると、モノの消費は適量になってゆき、結果的にモノづくりも適量になる。元々、僕たちには一つのモノを大事にする気質が当たり前にあったはずで。それゆえ、モノを買う時に対価の裏にあることまで気を配ることができていた。つくる人のことを考えて、対価を払って手に入れ、またつくる人の顔が見えて、また大事にして……その連鎖が、モノを持続させていく。それがサステナブルだと思っています。ARASが大事にしている考えは、お客様一人ひとりの“一期一会”になること。闇雲に量を生産し、販売することではありません。量産=均質な製品をつくる常識から疑い、量産であっても一期一会を生む血の通ったものづくりを目指しました。石川たとえば、こちらのカトラリー。実は、柄の部分は再生材を使用しており、まだら模様になっています。これらは、実は私たちプラスチック製造の中では“不良品”として扱われる種類のモノです。本来は捨てられる製品───なぜ、捨てられるのかというと、見た目が安定していないから。量産品の場合、一つひとつが同じデザインでなければ許されない。ARASは、その“本来、捨てられるモノ”を、あえて商品化のレベルへと昇華させています。上町さんが仰ったように、それぞれの表情が微妙に異なり、“一期一会”の模様になっている。ARASの隠れたコンセプトでもあります。 上町誰が決めたわけでもないのですが、金型を使用した工業製品の場合、「品質を安定させること(表情を含む)」が正義になっていますよね。また、大量生産という過程の中で再現性のある正確な色、カタチを均質にコントロールする行為が「プロダクトデザイン」の役割と捉える側面もありました。そこに疑問を抱いた。ARASでは、工芸品の現象によって生まれる"ゆらぎ"や"ムラ"にヒントを得て、工業用素材が自然に生み出す現象を制御しようとせず、引き出すという発想で開発をしました。結果として生産性を落とさず個々に個性を与え、お客様が潜在的に感じる「選ぶ楽しさ」や「自分だけのモノ」と思える気持ちと結びつけていくことができれば、永く愛でられるモノになるはずだ、と信じて。 嶋津石川さんの「企業の仕組みのアップデート」、上町さんの「“永く使える”ための、愛されるモノへの探求」。お二人にお話を聴くまで、その課題の存在自体をなんとなく見過ごしていたような気がします。一つひとつの模様が異なる製品を“不良品”と捉えるのか、“愛されるモノ”へと昇華して新しい価値を提示するのかでは、同じ素材を扱っていても、受取り手の体験や物語は大きく変わってきますね。________________________________________視聴者の声をピックアップしながら、開発者とデザイナーの視点から答えていく。セッションの一部を紹介したい。〈コメント〉ARASの商品はシンプルかつスタイリッシュで素敵です。カラーがダークなものが多いのは理由があるのでしょうか?上町色を決める時に大事にしていることは、あくまで“より良い食体験”を追求すること。器単体としてきれいな色であるということはもちろんですが、食材が盛り付けられた時に「おいしそう」と感じる背景色。ビビットなお色は、鮮やかであるがゆえに食材の色がくすんで見えます。鈍い色の前に鮮やかな色があると、より艶やかに映る。また、自然界には原色は意外と少ない。食材は有機物です。自然の世界に存在する色の方が相性はいい。食材という主役を引き立てる名脇役に徹しています。 〈コメント〉ARASのお皿やカトラリーは壊れにくいので、親から子へ受け継がれるし、もらった子どもはうれしいですね。石川実際、私も3人の娘を持つ親で、基本的に食卓にはARASの器が並ぶのですが、子どもと一緒のカトラリーやお皿を使えるのはうれしくて。器が、子どもを“子ども扱い”しない。実は、ここにもARASの隠れたコンセプトがあります。親と子ども、ないしはおじいちゃん、おばあちゃんまで、一緒の食器を使える。そこが伝わっているのがうれしいですね。________________________________________ 開発者とデザイナーの建設的な対話 印象的だったシーンは、視聴者からの質問に答える石川さんが「上町さんの“むちゃぶり”が難しく…」と話した場面。思わず「どのようなやりとりが交わされているのですか?」と伺った。その一連を知り、二人のモノづくりに対する誠実さを感じた。ARASは、チームの理想的なコミュニケーションの上に成り立っている。石川マグカップに関しては、これ以上ない機能性のプロダクトだと思っています。厚みがあり、熱を通しにくいので手に取りやすく、重心が下にあって、洗いやすい形状で、かつ口元は薄く、飲む時の舌触りまで考え抜いて設計されている。 この厚みの差が絶妙で、再現するには難易度が高く、製造する上でかなり苦労しました。特殊製法も編み出しているほどのレベルです。私たちの技術が上がれば上がるほど、seccaさんの要望がそれを少しだけ超えてくる。それも0.5だけ超えるイメージなので、必死に努力すればできてしまう。できるのだけれど、それに伴う労力は計り知れない。上町これまでの“樹脂”という素材の使われ方は、陶磁器や硝子でできた器の代用品として扱われてきました。“置き換え”であるから、陶磁器や硝子など“ホンモノ”と呼ばれる器での食体験よりも劣った印象になる。普通に考えれば、薄い形状にする必要はないわけです。ただ、僕たちは「この素材だから得られる形」を追求することで、“樹脂”の新しい価値を提示することにしました。そのためにも、理想を突き詰めています。石川樹脂さんに投げかけると、ポジティブな会社なので「できない」とは言わない。まずは「やってみます」という返答がくる。「うまくいかないけれど、こうやったらできるかもしれない…」という対話を重ねながら、妥協のない形状を追求できた。結果として、少しずつ要望は上がっていきますよね(笑)。嶋津こよなく建設的な関係性ですね。お話を聴いていて気付いたのですが、コンセプト設計から課題の発見、解決と、上町さんの立ち位置は、単純に“プロダクトデザイナー”というだけではないのですね。上町日本では“デザイナー”といえば、「色や形をつくる人」として認識されることが一般的ですが、僕の意識は違います。現状の課題を把握して、未来を描きながら、デザインという“方法”で解決してゆく。意匠を考える前に、クライアントのビジョンを総合的に見て、「最も良い形は何か」を考えるところからはじまります。課題や問いを発見し、それらを明確にした上で、意匠によって解決する。それが、僕の考える“デザイナー”です。それを仕事として受け入れてくださる企業はまだ少なく、石川樹脂工業さんは当初から、ビジョンやコンセプトをつくるところから頼ってもらえた。その関係性が僕としてはうれしいものでした。ARASが生まれたのも、そのパートナーシップを結べたことが大きかったように思います。石川上町さんと僕の共通する部分は、“馬鹿”がつくほど真面目なところだと思っています。「何が正しいのだろう」、「お客さんにとっての価値とは何だろう」と真剣に話し合って、一つひとつ検証してゆく。そこには数えきれないほどの議論と検証の数があります。どちらか一方だけの熱量だけだとしたら、これほどまでに実直で、建設的な議論を続けることはできなかったと思います。________________________________________ ~サステナブルコレクション~森を守る「杉皮の皿」~ ライブは佳境に入り、ARASの新シリーズ「サステナブルコレクション」が発表された。 上町ARASのトライタンという素材ではなく、ポリプロピレンという材料を半分使用して、もう半分は天然の杉の皮を使用しています。山の保全や林業の現状には「杉を消費しなければならない」という課題があります。中でも、「杉の皮」には使い道がありません。その素材を使用することで、樹脂使用料を可能な限り削りつつ、環境問題に還元できる。そのような思想でつくりました。石川ご覧になっていただくとおわかりの通り、一点一点の表情が異なります。杉の皮は天然物ですので、夏は薄く、冬は厚い。山地によっては、色も厚みも形も匂いも違う。原料として扱うには非常に難易度が高く、そのような意味でも今まで世の中に存在していなかったプロダクトとなります。「これこそがサステナブル」というARASの象徴的な製品となりました。 上町素材が揺らぐ余白を厳密に設計しています。どれだけ暴れさせて、表情にゆらぎを起こすのか。枠組みは決めて、こだわりをもって設計しています。僕たちが大事にしているのは、環境を守る取り組みや、食体験を豊かにするデザイン、一期一会のためのムラ感など。その内、どれか一つだけが秀でていてもダメで、全体のバランスを考えながら設計しています。このコレクションはまさに環境問題につながり、それがそのまま愛せるモノになる。________________________________________ 最後に 上町前職から、ものづくりに関わってきたのですが、独立するにあたり憧れの目標がありました。それは、直接お客様の顔を見て、製品を手渡しすること。一人ひとりと直接コミュニケーションすることは簡単ではありませんが、オンラインの力によって今日のような形が実現しました。この相互関係を大切にしながらモノづくりができているこの状況が幸せです。お客様の視点を開発にうまく取り入れながら、今後も「愛されるモノ」をつくっていきたい。そして、ARASはそれを最も体現できるブランドでありたいです。石川「ARASのそもそものゴールは何だろう?」という話を、時々開発メンバーと語り合います。私たちのゴールは、ARASの商品をお客様に買っていただくことではなく、ARASの商品を使用していただいて、お客様の日常の食生活が少しでも楽しく、豊かになるということ。私たちの力だけで環境問題が解決するのかというとそんなことは全く思いません。想いを伝え、モノを届け、考えに共感する仲間が増えれば、より大きな動きになる。そこでようやく、社会は少し変わるのかもしれません。まだまだ至らぬ点は大いにありますが、そこに向かって商品開発をしていきます。ご意見をいただきながら、皆さんと一緒に心地良い食生活をつくっていきたいです。
もっと見る
デザートで華やぐARAS小皿スロープ。Restaurant L’aubeシェフパティシエの平瀬祥子さんによるファッショナブルな盛り付け。自分の「好き」は、気分を高めてくれる魔法。【後編】
前回に引き続き、Restaurant L’aubeシェフパティシエの平瀬祥子さんとARASのデザインを手掛けるsecca inc.代表の上町達也さんの対談、その後編です 《平瀬祥子》ホテルニューオータニ熊本で料理の世界へ。2003年渡仏。パリ最古のパティスリー・ストレーで研修をスタート、2年後にはパティスリー・パスカルピノー・パリのスーシェフに。エッフェル塔内レストラン・ジュールヴェルヌ・パリを経てレストラン・トヨのシェフパティシエ就任。2011年帰国。エディション・コウジ シモムラ、 レストラン・アイの シェフパティシエを務める。2016年シェフ今橋英明氏とレストラン・ローブ 開業。2018年度版〜2020年度版ミシュラン一つ星獲得。2020年度ゴ・エ・ミヨ ベストパティシェ賞受賞。 自分の「好き」に、素直に。 感性の赴くまま、自分の「好き」に素直に、平瀬さんはデザートを盛り付けてゆく。時にファッションを楽しむように、時に目にした風景を再現するように、時にアーティストの気分で、時に大切な人に贈るギフトのように。それは、魔法のように見る人のこころをぱっと明るくする。 ──平瀬さんに盛り付けられたデザートを見ているだけで、気分が華やぎます。盛り付けにおいて普段意識していること、さらには平瀬さんの視点から「家で楽しめる盛り付け」についてのアドバイスをお聞かせください。 平瀬お菓子って、料理よりも飾りが多いと思うんですね。それって、女性がお化粧したり、洋服を選んだり、おしゃれすることに近い感覚だと思っています。素材そのものをドンっと置いてプレーンな状態で味わうことも良いけれど、ファッションのようにおしゃれを楽しんでもらうことも大事にしています。それぞれのパーツ(食材)がお皿に合うかというのは、トータル的なバランスで決めています。 上町チーズケーキとクランベリー、そしてピンクグレーの器、それぞれの色彩の組み合わせはまさにその考え方が基ですね。さらに言えば、振りかけた胡椒が風味とビジュアルどちらにもアクセントになっています。チーズケーキに胡椒という組み合わせは、僕たちには到底思いつかない。 平瀬「デザート」の枠を外して「料理」として捉えると、いろんな解決法が見えてきます。パティシエと料理人の考え方って全く違うんですね。私はレストランの経験が長かったので、その思考が影響しています。シェフの今橋(Restaurant L’aube)に「デザートの仕上がりが重たいんだけど」と相談すると「酢を足して見たら?」「胡椒をかけてアクセントにするのはどう?」「トリュフをかけてみる?」などのアドバイスが次々と返ってくる。料理人との会話の中で、そういう発想が日常となっていきました。お菓子に合う材料だけでまとめようとすると、おそらく私自身の個性が出ない。いわゆる“普通”のデザートになってしまうように思います。もっと自由でいい。 上町平瀬さん好みに味変して、盛り付けに反映させているのですね。正解をなぞるように盛り付けするよりも、遊びごころを持って「自分好み」の味を探すようにスパイスを扱えるようになると楽しそうですね。 みんな、“なんとなく”盛り付けていると思うんです。なんとなく「シフォンケーキに生クリーム乗せて、ミントを置けばいいんじゃないか」といったように。 平瀬「ミントを飾っておけばどうにかなるだろう」という考えはもったいないですね。全ての盛り付けが同じ形になってしまいます。ミントなどのハーブ系は、それが必要な味わいなのであれば飾りますが、そうでない場合は飾りません 上町新しく「自分好み」にチューニングする。ガトーショコラには、2種類のクルミが生クリームの上にかかっているのですが、それは風味とも強く関連していますが、その造形が盛り付けのアクセントになっている。風味の設計図をそのまま可視化した美しさを感じます。 もてなす「あなた」を想像する 平瀬誰かを招いておもてなしする時、相手がもし甘いものが苦手な人であれば、お酒に合うようにスパイスを利かせたり。逆に甘いものが大好きな人には、生クリームを乗せてあげたり。「誰が食べるか」というポイントでアレンジしてゆくと楽しいかもしれません。そうすると、同じケーキでも盛り付けは少し変わってきます。 上町マカロンの時も、お客様に合わせた絵柄を描いてお渡ししていたと仰っていましたね。一人ひとりに対する心配りにも盛り付けのヒントがある。 平瀬私が実家に住んでいた頃、母の手料理を食卓で食べる時に、家族それぞれの器が色分けされていたんですね。お正月の時は、箸置きがそれぞれ色違いだったり。お父さんはこの色で、姉はこの色が好きだから、と。そのような家庭で育ったので、なんとなく自然と誰しもに好きな色があるものだと思っていて。 お店では、リピーターのお客様に対しては「明るい色が好きだから、ピンクにしよう」など、その人に合わせて色合いを選ぶこともあります。フレンチでは「同じテーブルの人は、同じ皿を出さなければならない」という暗黙のルールがあるのですが、私はせっかくお客様の見える距離にいるのだから、その人が喜びそうな色を選ぶことも一つの楽しみのような気がしています。もてなす側の意識ですよね。 上町「お母さんが自分のために選んでくれたことがうれしかった」という原体験に由来している。「もてなしたい」という時の器の選び方、盛り付け方。お客さんへ出す時はその人との思い出や印象を添えて。「わたし」と「あなた」にしかわからないコミュニケーションツールだと思って色を選ぶことも一つのギフトですね。 色の楽しさ 上町今回の器は「家庭で使いやすいお皿」をテーマにしました。デザートを食べる時間をより華やかに、より楽しく過ごせるにはどうすればいいだろうと考えた。意外と、家庭でデザートを食べる時にしっくりくる器ってないんですよ。カップ&ソーサーの器にケーキを乗せたりすることもある。段差があるからケーキも歪むし、フォークできれいに切れない。それらの課題を解決した上で、目で見て楽しむことも重視したのが小皿スロープです。 今回、平瀬さんのデザートと器の関係性における色使いにたくさん発見がありました。普段、白や黒などシンプルな器を選びがちなのですが、ぼくたちももっと色を楽しんでいいのではないだろうか、と。その中で、器の色の生かし方などあればお聞かせいただけるとうれしいです。 平瀬とても使いやすいので、自宅でもこの器で盛り付けすることがあります。最初、ピンクグレーのお皿が扱いづらい印象だったのですが、使っているうちに愛着が湧いてきて。最近では、鱧を湯引きしたものをバーナーで炙って、菊の花を上からざっと散らしたのですが、白身魚の炙って焦げた色と、菊の花びらの黄色が、ピンクグレーの皿に映えてとてもきれいでした。ずっと使っていると、今までと異なる色合いが見えてきて楽しくなります。例えば、クリームブリュレなど表面が焦げた色にも合うし、秋の食材とも相性が良い気がします。色味のある器も使い続けているうちに、映える料理が見えてくる。そこからだんだん盛り付けが楽しくなってきます。
もっと見る