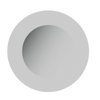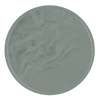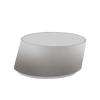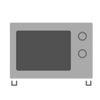ARASマグカップに湯気立つCAFE FACONのコーヒー。岡内賢治さんが香りと味で、気分と時間を演出する。日常に溶け込んだ「心遣い」とは。【後編】
ARASのJournalでは、ご家庭でARASの使い方や盛り付けの幅を広げていくため、定期的に料理人さんとのコラボ対談を行っています。前回に引き続き、CAFE FACONオーナーの岡内賢治さんとARASのデザインを手掛けるsecca inc.代表の上町達也さんの対談です。コーヒーの風味、器との関係性、そして、それらの背景にある「心地良さ」について。

《CAFE FACON》
中目黒と代官山(ロースターアトリエ)にあるスペシャルティコーヒー専門店。コンセプチュアルな店づくりとオリジナルにこだわったメニュー(自家焙煎コーヒー、自家製スイーツ、サンドウィッチ)。ミシュランガイドで星を獲得している一流レストランをはじめ、国内外で活躍する有名シェフのブーランジェリーやパティスリーでオリジナルのコーヒー豆を提供。2019年10月には、インドネシアのジャカルタにプロデュース店をオープン。
「心地良さ」をデザインする
「おいしい」は、コーヒーを飲む前からはじまっている。主張するモノだけでなく、溶け込んでいる要素の中に、「心地良さ」は隠れているのかもしれません。コーヒーとデザインの共通点。
──コーヒーを楽しむ時間、器のある生活など、お二人とも「モノが人へ届いたその先にある感情や景色」まで含めて大切にされているように感じます。どのような点を心がけていらっしゃいますか?
岡内
「喜んでもらいたい」という想いしかありません。そのために何ができるか。お客さん全員を「自分の家に来てくれたゲスト」だと思うと、やっぱり楽しんでもらいたいんですね。デート、打ち合わせ、一人の時間を過ごすため、会話を楽しむため……カフェには、様々な用途でお客さんが来店します。その時のお客さんを見て、その状況をいかに満足してもらえるか。
「今日ちょっと元気ないな」と感じれば、「どうすれば元気になってもらえるだろうか」と考える。それが「味」として伝えることができるのか、「コミュニケーション」で実現できるのか。常に、その時にいるお客さんを見ながらリラックスして楽しんでもらえる状況つくるように心がけています。

上町
テクニック以前の要素が大事なのだと思います。数値化できない部分ですよね。そもそも店への愛やコーヒーへの愛など、そういうレイヤーのこと全てが含まれます。例えば、店内に絵を飾るにしても、そこに愛がなければ、額装が歪んでいても見えません。違和感に気付くことができないんです。でも、「お客さんに心地良く過ごしてほしい」「絵を描いた作家さんが最も良いと思える状態で飾る」ということに意識を向ければ、1mmのズレにも気付くことができるはずで。大事にしている想いがあるかどうかが大切な気がします。
岡内
「こういうことをすれば喜んでもらえるんじゃないか」と自分なりに考える。まさに想いの部分ですよね。プロフェッショナルとしての技術や所作を洗練させることが前提ですが、リラックスしてもらえる空間づくりが先にあります。
例えば、オーダーを取りに行くこと一つにしても、せっかちなお客さんには早くお伺いに行った方がいい。のんびりしたお客さんにはあまり早くテーブルへ行くと急かされている気持ちになってします。人それぞれのペースがあり、それを崩されるとストレスになり、後の味わい方が変わります。同じコーヒーでも、イライラしているとおいいしいと感じない。つまり、一人ひとりのペースと調和することが大事なんです。ベストな状態でコーヒーを味わっていただくためには、環境づくりからはじまっています。
上町
「デザイン」というのは横文字で、ファッショナブルな印象があります。「かっこいいね」と言われるものをつくった方が、評価されているように感じます。ただ、生活に溶け込んでいるところにもデザイナーは存在しています。ロースターのパネルやドアハンドル、公共設備における目の見えない人に向けた点字や足場などのインフラもそうですよね。要は、一見地味だけど、誰かの人生を少しでも良い方向へ導くことに繋がっているもの。そのような価値を生んでいる部分が大事だし、僕自身関わっていたい。

かっこいいものを作ることはある意味簡単です。自己満足に近い部分があるので。表面的な自分の承認欲求を満たすようなことで、大事なものを見失わないようにしたいと思っています。「人の為」ということが最も心地良いはずなんです。だから、岡内さんのお話には強く共鳴します。自分の「我」のようなものを抑えることで、見える景色があるのかもしれないということが最近の発見です。
岡内
今回、ARASマグカップを見せていただいて、器へのこだわりが僕としてもすごくうれしくて。なかなかここまで想いを込めて作られたカップってないですよね。「デザインはいいけれど、使いづらい」という器は世の中にたくさんあります。この器は、手に持った時に「すごい」しかなかった。「使う人」のことを徹底的に考えている。
まず、取っ手のカタチ。大きさがしっくりくる。中指が取っ手に引っかかって、これがあるのとないのでは指への負担が全く違う。

上町
「てこの原理」によって、握らなくても持てるように設計しています。指でホールドする必要がありません。それゆえ、手への意識が軽減され、自然と味に集中できます。
岡内
意識せずにすっと持てる。ストレスがないんです。器の縁も薄く、口当たりへの心遣いも感じる。外側と内側の曲線部分にもこだわりが見えます。実用性を考えて、スタッキング(積み重ねる)できることもうれしいですよね。「どれだけ考えてこれを作ったのだろう」と。すごい発見というか、可能性というか……出会えてよかった。
上町
僕たちの想いを汲み取ってくださり、ありがとうございます。
色が与える「気分」というおいしさ
岡内
どういう味をつくりたいかは、色で喩えます。風味や香りでそれぞれ色があり、それをパレットで混ぜるようにして独自の色をつくっていく。
上町
風味の可視化ですね。デザイナーの僕にはとてもわかりやすいです。「赤と緑は喧嘩するよ」みたいなイメージですよね。
岡内
柑橘系の味と色で喩えると、黄色や薄い緑になる。ベリー系だと赤やピンク。味の傾向と色が同じなんです。色を重ねることで、どういう風味になっていくのかが見えてくる。
上町
色と風味の関係性はおもしろいですね。人は、色を認識した時に何かしら印象を受けます。先ほど岡内さんの話していた、オーダー時のペースを調和させるか、乱すかで味が変わるという話と近い部分がありますよね。例えば、カップの色の情報によっても味に影響を与える。

岡内
色で、その時の味は変わりますよね。中目黒の店では、様々な柄の器を使っています。毎回、その時のお客さんの雰囲気を見て、選ぶようにしています。いろんな器を楽しんでいただきたいので、基本的には前回来店した時とは違う器をチョイスする。少し元気がなさそうであれば明るめの器を選んだり、仕事でシャキッとしているイメージであればシャープな器を選んでみたり。「観察して選ぶ」ということが僕たちとしても楽しい。
上町
飲む人の雰囲気や気分によって、そのようなアプローチができれば有意義ですよね。これからの仕事における「働く意義」のヒントが詰まっている気がします。マニュアルではなく、働いている人の個性や感じ方によっても、選ぶ器は異なってくる。その属人的な心遣いにこそ、僕は未来の可能性を感じてしまいます。
Restaurant L’aubeさんとのお付き合い
上町
Restaurant L’aubeさんとは十年前からのお付き合いということを聞きました。レストランでも岡内さんのオリジナルブレンドのコーヒーが飲める。日頃、どのような会話をしながら豆を選定されているのでしょうか?
岡内
パティシエの平瀬さんがデザートを切り替えるタイミングで声をかけていただきます。「次のデザートはこのようなイメージです」と、それを受けてブレンドする。僕は今橋さんと平瀬さん、二人の作る料理とデザートが大好きなので、傾向はなんとなくわかります。メインの料理を聞けば、それに合うコーヒーも決まってきます。ただ、レストランにおいて、コーヒーはメインではありません。デザートに合わせる時は、あくまで主役はデザート。主張が強過ぎてはいけない。料理やデザートに寄り添う味を一番に考えています。二人も僕のコーヒーを信じていただいているのでやりやすいですね。
次号のJournalはRestaurant L’aubeの平瀬祥子さんと上町さんとのコラボ対談です。お楽しみに。