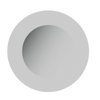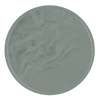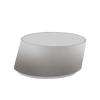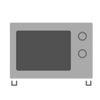ARASマグカップに湯気立つCAFE FACON(カフェファソン)のコーヒー。岡内賢治さんが香りと味で、気分と時間を演出する。日常に溶け込んだ「心遣い」とは。【前編】
________________________________________
ARASのJournalでは、ご家庭でARASの使い方や盛り付けの幅を広げていくため、定期的に料理人さんとのコラボ対談を行っています。今回は、CAFE FACONオーナーの岡内賢治さんとARASのデザインを手掛けるsecca inc.代表の上町達也さんの対談です。新商品のARASマグカップとのコラボレーションとして、3つのシーンに合うコーヒー豆を岡内さんにオリジナルでブレンドしていただきました。

________________________________________
《CAFE FACON(カフェファソン)》
中目黒と代官山(ロースターアトリエ)にあるスペシャルティコーヒー専門店。コンセプチュアルな店づくりとオリジナルにこだわったメニュー(自家焙煎コーヒー、自家製スイーツ、サンドウィッチ)。ミシュランガイドで星を獲得している一流レストランをはじめ、国内外で活躍する有名シェフのブーランジェリーやパティスリーでオリジナルのコーヒー豆を提供。2019年10月には、インドネシアのジャカルタにプロデュース店をオープン。
《ARAS item》
「グリーングレー」「グレー色」「ピンググレー色」3色のマグカップ。
_______________________________________
お客さんの「人生の一部」となる
岡内
「FACON(ファソン)」は、フランス語で「流儀」という意味です。僕の流儀を押し付けるのではなく、「僕はこれが素敵だと思うから、一緒に楽しんでほしい」というスタンス。コーヒーも、ブラックが苦手であればミルクやお砂糖を入れてもらって構いません。深煎り豆でも「軽めがいい」という人には要望に合わせた風味をドリップで抽出して提供しますし、熱々のコーヒーが好きな人には熱々で提供します。その人が「おいしい」と思う飲み方で楽しんでもらうのが一番良い。
上町
立ち位置が素敵ですね。この場所には、岡内さんでなければ生まれない時間や体験があります。コーヒーだけでなく、この空間に触れた人がハッピーな気持ちになるきっかけが散りばめられている。お客さんにコーヒーを提供する上で、「味」以上に大事なことなのかもしれません。おこがましいですが、僕たちが価値を置いているポイントと近い感覚だと思っています。
岡内
「誰が来ても、楽しめる」というカフェが僕の理想です。子どもからおじいちゃんおばあちゃんまで、分け隔てなくなく来てくれて、それぞれに楽しめる空間。実際に、店に通っていたカップルが「結婚するんです」と報告に来てくれたりすることもあります。お客さんの人生の一部になる、そういう場所でありたいと思っています。

________________________________________
上町
今回、岡内さんに「一日の始まり」「仕事のおともとして」「夜のほっと一息つきたいとき」の3つのシーンに合わて、それぞれコーヒー豆をブレンドしていただきました。

岡内
コーヒー豆は、品種もたくさんあり、土壌によっても個性は異なります。焙煎は、それぞれの豆によって最良の焙煎ポイントがあり、その性格に合わせて焙煎を変えています。焙煎度合いを見極め、実際に焙煎をしながら微調整を行っています。「アフターミックス」といって、それぞれシングルで焙煎した後にブレンドしてイメージの風味へと近づけていきます。

〈一日の始まり〉
コロンビア、グァテマラ、コスタリカ
岡内
グァテマラの中煎りの豆は、良い酸味とコクと甘味があります。同比率でブレンドしたコスタリカの豆はマイルドでミルクチョコレートのような印象。冷めてくると青りんごのような爽やかな酸味が現れます。コロンビアの豆は単体では個性は薄いですが、全体の味を一つにまとめてくれる役割があります。朝は、「一日のはじまりとして気持ち良くスタートしたい」という気分で。パンと合わせた時にも邪魔せずに、美味しく飲めるブレンドです。
〈仕事のおともとして〉
エチオピア(ナチュラル)、エチオピア(ウォッシュド)、ケニア、ルワンダ
岡内
エチオピアのナチュラルの豆をベースに、エチオピアのウォッシュドの豆を組み合わせています。ナチュラルはベリー系、ウォッシュドは柑橘っぽい印象です。そこにケニアとルワンダの個性豊かな豆をブレンド。ケニアは蒲萄っぽく、ルワンダはオレンジのような風味。フルーティなテイストをまろやかに楽しんでいただこうと思い、中煎りにしています。仕事の合間は、少し気分をリフレッシュしたい。香り立つ豆で「気持ちを切り替えてがんばろう」というイメージです。
〈夜のほっと一息つきたいとき〉
ペルー、コロンビア、ケニア、エチオピア(ウォッシュド)
岡内
全て深煎りの豆です。飲むとゆっくりと身体に染みこんでいく。深煎りの豆には、食後の消化作用を助ける効果があります。寝る前であれば、ミルクと合わせてカフェオレでお召し上がりいただくとよりリラックスできます。
________________________________________
岡内賢治とCAFE FACON
「コーヒーをはじめたきっかけは?」という問いに、「何でもよかったんです」と岡内さんは答える。大学を卒業後、就職した岡内さんは人事の部署に配属された。入社希望の学生たちと日々向き合う中で、理想と現実のギャップに違和感を覚える。
*
岡内
僕のことばを信じて入社してくれたのですが、しばらくすると「話が違う」と言って辞めていく者を何人も見てきた。誰にとっても「新卒」は、一生に一回しかありません。とても申し訳ない気持ちになった。次第に、「自分がつくったもので、人に喜んでもらえる仕事がしたい」と思うようになっていきました。
*
5年続けた仕事を辞職して、コーヒーの世界へ進んだ。周りからは反対された。既に結婚していた岡内さんには家族を養っていく責任もあった。その時、奥さまが「あなたがやりたいのであれば」と背中を押してくれた。
*
岡内
コーヒーじゃなくてもよかったんです。きっかけはサラリーマン時代に上司に連れて行ってもらった喫茶店。そこのコーヒーがおいしかったことで惹かれましたが、それ以上に「人に喜んでもらえる仕事」がしたかった。
数々のコーヒーショップを巡る中で、ある日、衝撃的な一杯のコーヒーと出会う。苦味の中に、甘味があり、果実のような酸味を感じた。明らかに今まで飲んできたコーヒーとは違った。豆にこだわった、自家焙煎の店。岡内さんの中で、「こういう店をやりたい」という明確な想いが芽生えた。
いくつかのコーヒーショップで働いた後、岡内さんはネルドリップの名店「アンセーニュ・ダングル」へと辿り着く。
*
岡内
アンセーニュは、想像以上に厳しい環境でした。マスターのきめ細かで鋭い感性は、コーヒーの味だけに留まりません。最初は、指摘する部分に気付くことができないんです。例えば、マスターが店の扉に向かって「いらっしゃいませ」と言う。そこには誰の姿もないのですが、次の瞬間、お客さんが入ってくる。あらゆることがそのような調子で、マスターにだけは「見えている」んです。そのことに深く感動しました。
「僕たちには気付けないのに、どうしてこの人には気付けるのだろう?」
マスターを観察していると、だんだんわかってくるんです。影の動きや微かな物音など、気付くポイントがある。最初は全くわからないのですが、五感を研ぎ澄ませてゆくと気付けるようになってくる。コーヒーの技術はもちろんのこと、所作、立ち居振舞いも美しい。どうしてもマスターの感性に近づきたくて、日々鍛錬を重ねました。
*
ダングルに入店した時、岡内さんは32歳だった。はじめの2年は、自由が丘店のマスターの下で働き、3年目からは原宿店の店長を任されるようになる。
*
岡内
原宿店はダングルの一店舗目でした。マスターが最も思い入れのある場所です。前任の店長が抜けたタイミングでもあり、売上も芳しくなかった。だけど、なんとか存続させなければいけない。責任のある任務でした。
*
苦戦を強いられる日々が続いたが、原宿店に移って3年目、一気にお客さんが増えた。ダングルのマスターの美意識、コーヒーの技術と知識、岡内さんの「人を喜ばせたい」という強い想い、それぞれが調和して「店」という一つの空間を形成してゆく。口コミが新しい客を呼び、リピーターが増えてゆく。原宿店の再生を成功させた岡内さんは、40歳で独立を決意する。2008年9月、中目黒にスペシャルティコーヒー専門店『CAFE FACON』を開業。
________________________________________
【後編】へとつづく