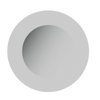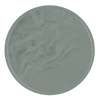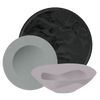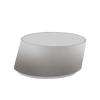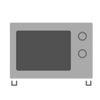ARASで、「持続可能なモノづくり」を実現する。石川樹脂工業とseccaが、樹脂で世界を変える
取材 / 文 : 嶋津(ダイアログ・デザイナー)
_______________________________________
今、「サステナブル」を発信する意味
「この一年で、大きく風向きが変わった」と石川さんは答えた。時代の潮流に加え、コロナ禍の影響により、世間の価値観は急速に変化した。就職面接の現場では、学生の質問内容に明らかな変化が見られた。以前までは給与や企業形態に関する質問が一般的だったが、最近は「何のための会社なのか?」と訊かれる機会が増えたという。企業が社会の中で果たす役割に、若者が強い関心を抱いている。加えて、取引先とのコミュニケーションにおいても「石川樹脂はSDGsに対してどのように貢献しているのか?」という問い合わせが増えた。「ここで一度、メッセージを打ち出す必要がある」と石川さんは続けた。
 素材としてのサステナブル
素材としてのサステナブル
「永く使える」という考え方をベースに
ARASをつくる背景の中で、彼らは「サステナブル」の考え方を再定義した。地球環境と共生し、持続可能なモノづくりとは何か。secca代表の上町さんは「価値観の伝播と視点の共有がミッションである」と話した。
当初、世間では「プラスチック=すぐに捨てられるゴミ」というイメージがあり、海洋ゴミを筆頭に樹脂という素材が悪役として扱われていた。議論を重ねる中で、プラスチックにも再生可能な素材があること、焼き物よりも低温で生成できるためCO2排出量を抑えることができるなど、樹脂の素材としての魅力を知ってゆく。効果的に使用すれば、今までにない価値を届けることができる。問題の本質は、「捨てる」という行為であり、「捨てられるモノ」が生み出されること。「多くの人が抱く樹脂に対する偏見を、素材から切り離して、新しい認識に置き換えたい」と上町さんは話した。ARASでは、ガラス入りトライタン樹脂というリサイクル可能な新素材が採用された。
また、「リサイクル」が手放しに推奨されている現状にも問いを立てた。つくる、消費する、再生する、あらゆる工程でそれぞれにエネルギーはかかる。それよりも、一つのモノを「永く使えること」が大切なのではないだろうか。そこで、「強く、美しい、カタチ。」というキーメッセージが生まれた。

構造としてのサステナブル
「安くて、良質」という呪い
ARASにおけるサステナブルの思想は、素材面に留まらない。生産、廃棄、再利用における循環の中での構造にも現れている。日本の現場でよく目にする安くて、手間のかかった良質のモノ。たとえば、量販店では手づくりの商品が安価に販売されている。石川さんはそこに強い違和感を覚えた。
石川:
私は「安くて、良質」は呪いだと思っています。具体的には、「手間のかかった低価格の商品」を指します。「高級品で、良質」ならわかります。安ければ消費者は喜ぶかもしれませんが、その裏では誰か(つくり手)が泣いているわけです。最低賃金やそれ以下で労働している人がいる。それは果たして正しいモノづくりでしょうか。その状況を変えたいと思いました。
単に「人件費の安い国でつくればいい」という話ではない。それは、場所を変えて別の人を買い叩いている行為であり、本質的な問題を解決していることにはならない。加えて、その国の経済が成長すれば、そのビジネスは10年、20年とは続かない。それが「持続可能である」と言えるだろうか。
これらの問題を解決する一つの答えが「製造工程の自動化」だった。石川樹脂では、ロボットを導入し、人手をかけない仕組みづくりに積極的に取り組んでいる。利益を追求する手段としての大量生産ではなく、誰かが泣いている状況を回避するための自動化。そこには大きな違いがある。思想の有無だ。「安くて、良質」という呪いが、「技術と思想」によって祈りに変わる。

石川:
検品や梱包に関しては、まだ人の手に頼っていますが、ゆくゆくはそれらの工程も自動化し、可能な限り無人に近い状態を目指します。「安くて、良質」でありながら、誰も買い叩かないサプライチェーンを実現する。

さらに在庫と廃棄の課題にも取り組んでいる。アパレル業界では、シーズンごとに様々なカラーやサイズの服が大量にリリースされ、売れ残ればセールに出され、それでも買い手が現れなければ最終的に廃棄されることが問題視されている。数をつくればいいというわけではない。「捨てる」という行為と、「捨てられるモノ」を失くすためには、適量の供給を実現する必要がある。
石川樹脂は、自社工場ならではの強みを活かし、最小限のロット数で生産することに成功した。抱えた在庫に合わせて、品数が薄くなればその場でつくる。販売経路は、自社サイトがメインだ。今まではメーカーと消費者の間に、一次卸、二次卸、小売店が介在していた。その仕組みでは「どの商品が、いつ販売され、どれだけの在庫を抱えているか」という情報が届くのも遅い上、売れ残ればそれらの製品は廃棄されていた。
石川:
今までは壮大な情報とモノを無駄にしていました。今では自社サイトにおいて、お客様と直接コミュニケーションして、在庫も全て私たちが一元管理しています。受注状況もリードタイムも把握できる。もちろん小売店にも協力していただきながら進めていますが、在庫に関してはロスが生まれないよう数量を絞っています。
DtoCという仕組みを、流通によるコストやデジタルマーケティングという観点ではなく、
「適量をつくるための仕組み」として捉える。大量消費を促すための生産ではなく、求められた声に合わせて数量を調整してつくる。結果、「環境との共生」という価値軸で持続可能な構造を実現した。

精神としてのサステナブル
デザインが引き出すマインド
seccaが石川樹脂にコミットする以前はデザイナー不在で、取引先の意向に従って量産品の形状を決めていた。たとえば、ガラスをトライタンに置き換えた器などの模倣品──いわゆる〝ニセモノ〟と印象付ける本意ではない樹脂製品が求められた。「それだと、つくり手もつくっているモノに対して愛着が湧いてこないんです」と柳井さんは語る。石川樹脂の丹精込めた丁寧なモノづくりを見て、足りないのは「モノに対するアップデート」だと気付いた。
柳井:
レストラン向けに器をつくるのも、エンドユーザーである料理を召し上がるお客様に向けていると思いきや、そこで働いているシェフやサービスの人に向けています。「お客様に、この器で盛り付けた料理を出してみたい」とわくわくしてくれる。つくる側の人の気持ちが上がってゆく。わくわくしている人たちから出された料理からは、いろんなモノが伝わってくる。それがとても大事で、その内的な誘発剤としての役割をデザインに含ませたいと思っています。実際に、僕たちのデザインした器を、石川樹脂の設計チームの方々が「いきいきとしながらつくっている」と聞いてうれしくなりました。

消費者だけでなく、「つくる人(製造者、料理人、サービスを含めた)」のこころをわくわくさせることができれば、それを見ている人たちにも良い影響が生まれる。「デザイナーの責任は内側にある」と上町さんは話した。器の接し方一つにしても、毎日大事に扱っている親の背中を見てきた子どもと、飽きると捨てて新しいモノに買い替える家庭に育った子どもでは、器の向き合い方は違う。つまらなそうにモノを扱えば、それを見て育った人は乱雑にモノを扱うようになる。
「東洋医学的な発想です」と上町さんは話す。大元を辿ってゆくと、価値を生む源泉にヒントがある。エンドユーザーだけでなく、「価値を生むためには何が必要か?」という問いを辿ると、デザイナーの役割はそこにあった。
「捨てられないモノをつくるためには、デザイン性が重要だ」と柳井さんは話す。デザインが良くなければ、途中で手放したくなる。試行錯誤を続ける中で、ディティールに凝った樹脂素材の食器が少ないことに気付いた。工芸の世界では当たり前のことが、工業の世界では未開拓のままだった。柳井さんは、徹底的に細部に向き合った。素材の持つ美しさをいかにして引き出すか。それがひいては、モノの魅力につながり、愛着へとつながってゆく。
柳井さんのことばを裏付けるように、ARASの製品は数えきれないほどの検証が行われている。取っ手一つを決めるにも10~20個のプロトタイプをつくる。人それぞれ手の大きさも違えば、重さの感じ方も違う。どこに基準を設定するかは、メンバー内で慎重に議論を重ねた。

柳井:
「平均化で合わせたものは、誰にも合わない」ということばを、普段から言っています。まず自分たちがしっくりこないと、それを共有したところで誰の共感も得られません。「良し悪し」という感覚は、個人的な感性なので一概には言えませんが、少なくとも自分たちが本当に納得できるモノ、「良い」と胸を張って言えるモノをつくる。
上町:
モノをつくる過程、あるいは、モノを生み出した後の「モノが介在することでできる人との関係性がどう変わるか」が、僕たちの関心です。正直な話、マジメにつくり続けていれば、ある程度、美しいモノはつくることができます。しかし、「そのモノがどのような影響を与えるか」までを考えることができる人は限られている。僕たちはそういうデザイナーでありたいし、そういう人が増えていく世の中にしてゆきたい。
器が触媒となり、マインド(精神)の部分でサステナブルになる。表面的に「持続可能か、不可能か」を議論してもあまり意味はない。デザインの力と、仕組みの力で、本質的な課題を解決する。上町さんの言った「価値観の伝播と視点の共有」は、言い換えれば「文化をつくること」だ。彼らは、樹脂によって人々のライフスタイルや価値観に大きな影響を与えている。

これからの展望
サステナブルの観点から、粘り強く問いを立て続け、一つひとつ解決してゆく。そこには常にチャレンジ精神がある。「意思決定の多さと失敗の多さでは大企業に負けない」と石川さんは語る。それは、アクティブに挑戦し続ける姿勢を意味する。2021年冬には、石川樹脂は新たなプロジェクトを立ち上げる予定だ。
モノを永く使うことは正義だが、それは急速にモノを消費するビジネスモデルが通用しないことを意味する。お客様にモノを売っているようで、コトを共有してゆくことが仕事になるかもしれない。そう上町さんは話した。
レストランにおいて、今まで陶磁器の食器、貴金属カトラリーが当たり前だった中で、新しい選択肢としてARASが採用されるようになった。選択肢の一つとなり、他の素材とも共存できている。今後はさらに、樹脂でなければ表現できない新しいポテンシャルを引き出し、樹脂の工芸的な表情を模索してゆく。柳井さんはそう語った。

石川さんは仕組みの面で随時改良をしていく意向を見せた。製品の回収の仕組みを整えること。宅配便に頼ると、トラックによるCO2排出によって無駄なエネルギーがかかる。そのため各地に回収スポット(サステナブルBOX)を設ける計画を立てている。国内に小売店が200~500ヵ所あれば、理想的なサイクルが実現できる。「まだまだ改善の余地はたくさんあります。それを一つ一つARASが大きくなるにつれて丁寧に解決していきたいと思います」と、石川さんはこの鼎談を締めた。
_______________________________________
素材、構造、精神、あらゆる軸で価値観のアップデートを起こす。ARASの「持続可能なモノづくり」は、樹脂を通して文化をつくり、世界を変える。この多層的なサステナブルが、美しい未来を実現する。