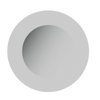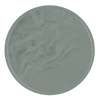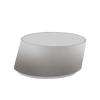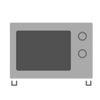ARASで、食卓に涼やかさと立体感を。岡川“ぽんた”透さんの創作料理と器のセッション。新カラー「スモーク」シリーズと「ななめ小鉢」で彩る日常の食卓。【後編】
ARASのJournalでは、ご家庭でARASの使い方や盛り付けの幅を広げていくため、定期的に料理人さんとのコラボ対談を行っています。今回は、PLAT HOMEオーナーの岡川“ぽんた”透さんとARASのデザインを手掛けるsecca inc.代表の上町達也さんの対談です。ARASの新カラー「スモーク」シリーズと『ななめ小鉢』の発売に際し、岡川さんにARASの器を用いて料理を盛り付けていただき、盛り付けの楽しみ方や器と料理の考え方などをお話いただいています。こちらはその【後編】です。
プロの料理人さんのARASを使用する際の盛り付けの考え方や楽しみ方、実際の盛り付け例などをお楽しみください。
「つくり手の表情」が見える器

【材料】
エビ、イカ、マグロ、ヤングコーン、オクラ、金沢のふと胡瓜、スダチ、発酵させたプラムのソース。
小鉢①:薬味 わさび、刻んだ生姜の醤油漬け、セロリの佃煮。
小鉢➁:ごはん、アボカド。
岡川
このscoopの皿をはじめてもらった時に、「何を、どのように、盛ろうか?」ということを考えました。ふと、上町さんと出会った頃、この器について話してくれたことを思い出した。(※ジャーナル上町さんの記事リンク)計算された器なんです。
上町さんのscoopの考えと、僕の料理の表現を合わせて、「刺身をすくって食べるのはどうだろう?」と考えた。普通は、刺身をすくって食べることってまずありませんよね。体験としても楽しそうだ。
スプーンですくった時に、ぐにぐにしたものだけだとおもしろくないから、食感を楽しんでもらうためにヤングコーンを入れた。プラムを発酵させたオリジナルソース。薬味はわさび、刻んだ生姜の醬油漬け、セロリの佃煮。
そのまま食べてもらってもいいし、全部混ぜてもらってもいい。プラムの酸味とお刺身なので、酢飯感覚で食べてもらえるようにごはんを添えました。刺身としても、海鮮丼のイメージで食べてもらうこともできる。そのようなストーリーが自分の中にはあります。

上町
全てが「すくって」完成する。つくり手の意図を汲み取って、発想を飛躍させた。実にすばらしいです。

【材料】
イワシ、パプリカ、シソの花、えんどう豆のツル
岡川
大量の油でイワシを焼きました。オイル漬けに近いイメージです。オイルを下に溜めておいて、そこにイワシをのせた。ソテーしたパプリカや季節の野菜を。scoopは深さもあるから、汁物にも合う。溜まったスープが円形になるように設計されています。
「すくう」や「汁物を食べる」という使い方がしたかった。器の高さと幅のバランスを考慮して盛り付けました。
ハレの器、ケの器
上町
一般的な家庭だと、なかなか作家モノの器を使う機会がありませんよね。量産という仕組みの中で生まれた器を選択することの方が多い。「店」ではなく、「家庭」という視点になると、器の役割は変わるのでしょうか?
岡川
「量産品」って、出会いモノですよね。たとえば、ふと入った雑貨屋さんで「あ、この器、かわいい」という出会い方をする。
ARASのようなオリジナリティのある器は、出会った時のフィーリングで心が華やぎます。同じ家庭の食体験でも、「今日は誕生日だから」など、良いことがあった時に選びたくなります。
上町
僕は、家庭の器の役割は「愛着」だと思っています。料理屋で扱われる器は、料理人の表現の一部であり、店と客をつなぐインターフェースとしての役割がある。たとえば、そこに箸を置いた時に「結界を感じる」といったような。自分(客)の領域ではなく、相手(店)の世界に浸っている状態です。
家庭の器は、日々触れることで愛着へと変化していくのではないでしょうか。そこから、だんだん捨てられないモノになってゆく。
岡川
それは人によるかもしれませんね。器に対して愛着を抱く人と、「量産品だから」という理由でぞんざいに扱う人の差は激しいと思います。経年劣化を愛せる人と、そうでない人の違いとも言い換えることができるかもしれない。ARASの器が好きな人は、経年劣化を楽しめる人が多いのではないでしょうか。

上町
樹脂における経年劣化の景色は、これからの課題でもあり、楽しみな部分でもあります。あくまで、僕たちの考えは、今のサスティナブルの文脈を含め、新たな素材で「家庭の中の一つの選択肢」を提案すること。
岡川
サスティナブルという面に関して、とても心を惹かれます。その文脈がトレンドとして留まらず、これからも継続されるならば、ARASは「生活の中の器」のベーシックになっていくのではないでしょうか。一消費者として、世の中に広く伝えてほしいと心から思います。「デザインがユニークだから」というだけでなく、環境に対する配慮が込められている。
上町
その点が、僕たちの器を手に取ってもらうための一つの理由になっているのではないかと思っています。
ARASの魅力
──今回の創作料理を通して感じたARASの器の印象をお聞かせください。
岡川
長所として挙げられるのは、何より先に、使いやすさですね。あと、料理を発想するおもしろさ。器を渡された時に、「どの向きで盛り付けようか」と考えた。器を手に取っていろいろな角度から、「どういう表情が一番いいかな」と思索する。それは楽しい体験でした。
上町
思惑通りに悩んでくれましたね(笑)。レストランで樹脂の器を使用するならば、どのような意図があるのでしょう?
岡川
今回、僕はこれらの器を常温で使っています。触った時の温度感も、季節感につながる感覚です。たとえば、冷やした器だと表現も変わります。あるいは、温めることでも表現は変わる。樹脂だと常温使いが基本になりますよね。そこはメリットだとも言えます。
先日、A_RESTAURANT(※リンク先の添付)でカトラリーを使わせていただきました。冷たい料理を食べた時の「素材そのままの味がわかる」という体験がユニークでした。
たとえば、キンキンに冷えたものを、常温のステンレスのカトラリーを使用して食べた場合、熱伝導によって温度帯が変わります。自分の料理を作った時に、「これがベストの温度です」と出しても、お客さんの口の中に入る時には温度が変わってしまう。そうなると風味も変わります。ARASのカトラリーは漆と同じで、素材の温度をそのまま楽しめる。
上町
温度を演出したい時には、選択肢から外れるけれど、料理の温度をそのまま伝えたい時には樹脂でも選ばれる可能性があるわけですね。家庭だけでなくレストランにおいても、素材による使い分けの一つに樹脂が入れば、おもしろくなりそうですね。
対談を終えて
──岡川さんのおつくりになったお料理を、上町さんはどのようにご覧になりましたか?
上町
率直な意見として、期待を遥かに超えていました。scoopの「すくう」の解釈にも感動しましたし、ARASの器は家庭向けだけでなく、レストランでも十分選択肢の一つになり得るのではないかという可能性を感じました。
今まで「食」のコンテンツに足りなかったものは、考え方や視点なのだと思います。今回、その部分をシェアできることはうれしいですね。