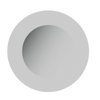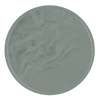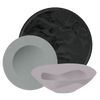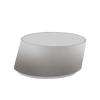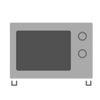山本理世さんのファラフェル。 料理を通じて、空間をコーディネートし、幸せをつくる。
Profile
R!CE FOOD DESIGN山本理世(フードデザイナー/出張料理人)
オーガニック野菜を使った創作スパイス料理やvegan料理を得意とする。
2017年に出張料理人としてR!CE FOOD DESIGNを設立し、食と空間デザインを融合、楽しい食体験を提案。 ケータリング、フードコーディネート、フードクリエイションなど多岐に渡り活動中。
ファラフェルについて
マッシュしたひよこ豆を揚げて、ソースと一緒に食べる中東のヴィーガン料理です。ヴィーガン料理とは、動物性の素材(肉・魚・乳製品)を使用せず、植物性の素材だけを使用した料理のこと。もともとヴィーガン料理は、動物愛護の考え方をもとに成り立っています。
ひよこ豆は淡泊な味という印象を持たれがちですが、この料理であればまた違った印象で楽しんでいただけます。わたしの中では、ファラフェルはひよこ豆を最もおいしく食べることができる料理です。
Vegan料理
スパイス香るファラフェル ( ひよこ豆のコロッケ )
ファラフェル (3~4人分)
材料
ひよこ豆 200g
にんにく 1 片
クミンシード ひとつまみ
コリアンダー 小2
玉ねぎ 1 個
パセリ 1/2 株
片栗粉 15g
(コーンスターチ)
塩 小1
パクチー 適量
(タヒニソース)
ピーナッツバター(無糖)大1
豆乳ヨーグルト 大1
塩 小1
米油 少量
レモン汁 5g
作り方
①ひよこ豆を半日~1日たっぷりの水で浸水させておく。
②鍋に30%の塩と水を入れ30分程ひよこ豆を煮る。(指で潰れるくらいですが、気持ち硬めで良い)
③ 玉ねぎをみじん切りにし、塩をひとつまみ加えフライパンで弱火~中火で炒める。
④フードプロセッサーに柔らかく煮たひよこ豆と、にんにく、スパイス、粗熱をとった炒め玉ねぎと塩を加えフードプロセッサーで粗みじんにする。
⑤パセリを加え、さらにかくはんさせる。

⑥片栗粉を加え、スプーンや手でぎゅっと押し固める用に形成する。
⑦形成したタネに片栗粉をまぶし、180度の油でさっと色づくまで揚げる。

⑧タヒニソースを作る。ピーナッツバターは少し油分(米油)を加えると練りやすくなるので、柔らかくなるまで練ります。そこへ他の材料を加え最後に塩で味を整えます。
⑨器にタヒニソースを入れ、揚げたてのファラフェルをのせ、パクチーを飾れば出来上がり。

スパイスとハーブが香る豆のコロッケ。
ヘルシーでコクのあるヴィーガン料理です。白ワインに合う料理に仕上げてみました。
揚がったひよこ豆に付け合わせとして、一緒に食べてもらうタヒニソースをつくります。タヒニソースは白ゴマペースト、豆乳ヨーグルト、レモン汁でできています。今回は白ゴマペーストの代わりにピーナッツバターのペーストを使用しました。
ポイント
ひよこ豆は乾物で販売されており、一度水に浸さなければ煮ても戻りません。水煮したものが販売されていますが、やわらか過ぎてべちゃべちゃになってしまいます。ですので、豆は買ってきたものを水で戻して自分で煮るのが理想的です。また、ぐつぐつと強火で煮てしまうと食感が損なわれるので、豆の質感を残しながら煮るというのは押さえておきたいポイントです。
硬い豆の方が質感をコントロールしやすく、食感を残したければひよこ豆をフードプロセッサーではなく、すりこぎ棒で潰して粒を残した状態で材料と混ぜると良いでしょう。
揚げる時の注意点は、材料に含まれる水分量。水分量が多いと油の温度が低くなり、油の中で具材がほどけてしまいます。本来、それを防ぐために小麦粉、卵、パン粉などをつけて揚げるのですが、この料理はそのまま素揚げするので、形状する時にぎゅっと水分を出すように握るのがポイントです。コンスターチ、あるいは片栗粉を加えて具材が離れないようにしても良いでしょう。
ヴィーガン料理に魅せられたきっかけ
前職の頃、渡米させていただく機会があり、ロサンゼルスへ行きました。その時、友人に連れて行ってもらったヴィーガン料理のレストランとの出会いが、わたしの人生におけるターニングポイントでした。
ヴィーガン料理というと日本では精進料理のようなイメージで、宗教的なカラーやストイックな印象がありました。ですが、そのレストランの印象はわたしが抱いていたイメージとは全く異なるものでした。
扉を開くと、若い男女がドレスアップして、ヴィーガン料理を食べながらお酒と一緒に会話を楽しんでいる。コース料理が出てくるような格式高いレストランというよりも、カジュアルな居酒屋のような場所です。それなのにヒールをはいて、それぞれにおしゃれを楽しみながら華やかに会食している。その光景が私にとっては衝撃的で、一瞬で惹き込まれました。料理と音楽、そしてテーブルコーディネートされた空間。味もそうです。肉や魚がなくても十分おいしく楽しめるのだということをその時はじめて知りました。
あのレストランを訪れたことで、わたしの抱いていたヴィーガン料理の印象はがらりと変わりました。そこでの体験から「食事の雰囲気や、料理を通じてライフスタイルを自分なりに提案したい」と思うようになりました。それが今の仕事をはじめたきっかけにもつながっています。
料理をつくるだけではなく、空間を含めてコーディネートしていく。
雰囲気や賑わい、そこに集まる人たちを含めて料理です。ヴィーガン料理を楽しんでもらうために「どんな雰囲気で食べたいか」「誰と食べたいか」「どんな会話がそこにあると楽しいか」ということについて深く考えました。自分でそのような食体験をつくっていくのが一番だと思い、キッチハイク(出張料理のサービス)に関わらせていただき、自宅ではなく、シェアホテル、器のお店など場所を変えて食事会を開催していきました。
「自分のフィルターを通して、ヴィーガン料理の魅力を自分なりに伝えていく」
ロサンゼルスでの感動をどのようにアウトプットしようかと日々、試行錯誤していきました。
ヴィーガン料理をよりおいしく、そして、ファッショナブルに。
まだ日本では、ヴィーガン料理といえば精進料理のような「味気がないもの」というイメージが根付いています。そのイメージをどのようにすれば変えることができるか。
まずは「おいしい」ということを伝えたい。乾物で食感を出したり、揚げて香ばしさを出したり、変わった食材を使ったり。調理の中でいくらでも工夫はできます。スパイスは洋風でいえばブイヨン、和風でいえば出汁みたいなものです。料理に奥行きや深みを与えます。味覚には甘味、苦味、酸味、塩味、うま味などいろいろ種類がありますが、それらを食材や調理法によって足し引きすることで味わいのバランスを整える。それをスパイスでコントロールすることによって深みを表現します。
また、スパイスは野菜との相性がいいので、野菜料理がとても深い味わいに変わります。ブイヨンを使わなくてもスパイスを入れるだけでぐっと味が引き締まる。工夫すればジャンクフードのような風味も表現できます。既存のヴィーガン料理のイメージを変えるには、インパクトのある味わいが役立ちます。お客様からは「ヴィーガン料理ってこんなに味の濃いものだったんだ」「肉・魚を使用していないのにどうしてこんなにおいしいんだろう?」といったうれしい反応をいただくことも珍しくありません。
例えば、今回の料理でつくったタヒニソースも本来は白ゴマペーストを使用するのですが、それだとソースとして薄くやさしい味になります。ピーナツバターのペーストを代用することで、コクが増す。白ワインとのマリアージュを楽しんでいただきたいという想いがありましたので、そのようなアレンジを加えました。
ヴィーガン料理を飲みものとの相性としても楽しんでいただけるように工夫する。お客様の選択肢を増やしてあげるということも大切だと思っています。それが「ヴィーガン料理」の新しい価値観を表現することへとつながります。
フードデザイナー、出張料理人として伝えていきたいこと
以前、ある人からクレイジーウェディング創設者の山川咲さんの著書『幸せをつくる仕事』を贈っていただきました。そこにはまさしく私が頭の中に描いていた世界が文章化されていました。
「幸せをつくる仕事がしたい」
みんなが幸せになるような食体験や日常の豊かさを私なりに料理を通じて届けたい。その想いから今の仕事をはじめました。
フードデザイナーとしての「私」も、出張料理人としての「私」も、同じ「私」です。違いは食体験を自宅でするか、外でするかというだけのこと。ちょっとした工夫次第で食事の空間はより楽しいものになります。料理は場所を選びません。これからもテーブルコーディネートによって「雰囲気を演出すれば毎日の食事が楽しくなる」ということを伝えていきたいです。